防災知識:ローリングストック法とは?
ローリングストック法の基礎知識entrance
来るべき災害に備えて、食料を備蓄しているという方も多いかと思われますが、大半の家庭では、おそらく長期保存が可能な非常食をまとめ買いして、納戸やクローゼットなどの空きスペース押し込んでいるのではないでしょうか。
ところが、最近、従来のこの方法に代わる〝ローリングストック法〟と呼ばれる新たな備蓄法が注目され始めているようです。
そこで、ローリングストック法とは何なのか・・・!?
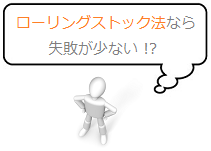
その特徴や推奨される理由(背景)、ローリングストック法ならではの欠点についても少し触れてみたいと思います。
ローリングストック法とは?
ローリングストック法(ロースト法)という備蓄法が、テレビや雑誌などの各メディアで広く注目されるようになったのは、2013年春頃のことです。
日頃の防災に役立つ知識や情報にスポットを当てながら、解りやすく紹介しているNHKの『そなえる防災』などでも取り上げられたこともあるので、ネーミングくらいはなんとなく聞き覚えがあるという方もいるかもしれませんが、実は国※も推奨している備蓄法のひとつです。
※内閣府の防災情報ページ(できることから始めよう!防災対策:第3回)にて紹介。
そもそも、ローリングストックというネーミングは、転がす(回転)という意味の「rolling(ローリング)」と、蓄えるという意味の「stock(ストック)」という2つの単語を組み合わせた言葉で、非常食を定期的に消費(食べる)しては、その都度、買い足す先入先出法(古いものから順に処分)の原理に基づいた備蓄法のことです。
では、いったいなぜ、このような備蓄法が注目され始めたのかというと、この点は特に東日本大震災の影響が大きいかと思われますが、従来の防災対策におけるこれまでの常識(考え方)が通用しないケースが出始めてきたからです。
これまでは災害発生後、2~3日もあれば、公的な支援物資は現地(被災地)に届くだろうという考えに基づき、備蓄食は3日分も用意しておけば十分というのが常識(一般的)でしたが、東日本大震災のような非常に広範囲に甚大な被害が及ぶような大災害に襲われると、3日どころか、ヘタをすると1週間以上、救援物資が届かない恐れがあります。
近い将来、発生する確率が高いとされる南海トラフ巨大地震や首都直下型地震(マグニチュード7クラス)などの大災害を考慮すると、従来の常識では不十分なのでは?という懸念から、非常食のあり方も見直そうという動きがあり、このような新たな備蓄方法が提唱されているのです。
ではここで、ローリングストック法の備蓄方法が、いまひとつよくわからないという方のために、図表等を使って説明しましょう!
| 家族の人数×4日分の食料(3食)を備蓄 | ||
| 消費した備蓄食を新たに買い足す | 定期的に備蓄食を食べる | |
| ※4日分の食料を備蓄し、1ヵ月に1食分づつ食べ続けると、ちょうど1年で備蓄した食料がすべて入れ替わる | ||

人によって、若干、蓄え方や消費の仕方に違いが見られますが、これがローリングストック法の基本的な考え方となります。
![]()
ローリングストック法のメリット
普段の生活で日常的によく使う食料品や日用品をはじめとした衣食住に必要な品を、いつもより少し余分に買い足し、ストックしておくことで、いざというときの非常事態に対処するというローリングストック法には、主に次のようなメリットがあります。
![]()
ローリングストック法のメリット
近年、防災のスペシャリストや関連企業などが、盛ん(?)に提唱しているローリングストック法ですが、必ずしも万人に有効な備蓄法であるとは限りません。
![]()
家庭における備蓄法を、ローリングストック法に切り替えたがために、かえって管理が煩わしくなったというケースも考えられるため、ロースト法を実践するかどうかは、家族の性格やライフスタイルを加味した上で、検討することが大切です。



